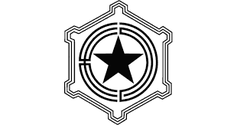ラーメン「富公」と祖父の思い出
狸小路7丁目にあった伝説のラーメン店「富公」が、もともとは当院の入居するビルの並び、カナリア裏で創業したことをたまたま知って嬉しくなった。しかも、それは、ビルの竣工する3年前の昭和36年だという。今から60年以上も昔、のちの名物店主がその若かりし日に実家の靴屋の廃業を機にラーメン屋になろうと志し、「味の三平」での修行を経て、今の私とほぼ同じ場所で奮闘されていたことになる。
私が「富公」を訪れたのは、まだ小学生の頃だったと思う。お店ののれんをくぐると、居並ぶ客に威勢良く指図するおっかない店主のおやじさんがいた。足を踏み入れただけで店内にみなぎる緊張感を私もビシビシと感じとっていたが、不思議と怖くはなかった。祖父がそばにいてくれたのと、おやじさんが子どもに注ぐ視線が優しいのがわかったからだ。そして、あっつあつのラーメンは本当においしくて、いつも頬を上気させて満足感とともに店をあとにした。おやじさんの一人舞台である厨房の向かって左奥には小窓があり、中にはおばさんがいるらしかった。そんな細部までがとてもよく記憶に残っている。そして、あんなにおいしいラーメンには二度と出会っていない。
(‥‥と思いかけたが、おやじさんの人柄と心意気がラーメンに乗り移った一杯がほかにもあった。旭川の「ラーメンふるき」だ。今は娘さんがお店を継いでいるらしい)
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
ところで、「富公」のおやじさんは、入ってくる客をにらみつけ、どこそこに座れとか、席をつめろとか言って、采配を振る。「ごちそうさまでした!」「おうっ!」という短いやりとりが繰り返される中でも、競馬ですった浪人生みたいなどうしようもない若者が「おいしかったです!またがんばってきます!」と宣言し、おやじさんが「こいつはどうしようもないやつなんだ、ハハハ」と言って茶化す場面に出くわしたこともあった。まだ小学生の私にも、そのとてつもなく美味い一杯でお兄さんはおやじさんに尻をひっぱたかれているのがわかった。
時は流れ、90年代に長い浪人生活を送る中で、時々あの「富公」にいたお兄さんを思い出すことがあった。私は、ある意味でどうしようもない若者になっていて、お兄さんと自分を重ね合わせたのかもしれない。その頃にはもう「富公」は閉店していたようだが、たとえお店があったとしても、とてもひとりでお店に入る勇気は無かったと思う。競馬場やらパチンコ店やらススキノに入り浸っていたというわけではない。むしろ極端にストイックだったのだが、予備校には行っていたものの、毎朝母にもらうお昼代をポケットに入れたまま、フラフラと札幌の街中のCD屋と本屋を巡り歩き、一体どこに向かっているかわからない数年を送った。自分でも何をしたいのかわからず、ただひたすらに英語参考書の名著を丸暗記するとか、心理学の本を読みふけるとか、CDを耳がおかしくなるまで聴きあさるとか、無理と無駄とムラの極致のような行為にいそしんでいた。札幌駅の弘栄堂書店や大通の紀伊国屋書店や旭屋書店、タワーレコード、HMVなどは特に懐かしく、今のクリニックの近くをさまよっていたのだと思うと感慨深い。
かつて「富公」に何度も連れて行ってくれた祖父は、母の父で、孫の私に美味いものを教えてやろう、というつもりだったと思う。祖父は、若くして妻を病気で亡くし、当時の落胆は大きかったという。公務員を辞めてしまい、母親曰く「グレた」のだそうだ。土建屋の社長をしたり、評論雑誌を出版したり、はたまた保健所の副所長をしていた経験を生かして焼肉店をやっていたこともあった(今ブームのサガリ肉のステーキを「ビフテキ」と呼び、御馳走してくれた。とびきりおいしかった)。いつも羽振りが良く、懐に札束をしのばせ、母によく小遣いを渡していて、のちに景観デザイナーとして父が独立する前のわが家の家計も助かっていたようだ。肺がんを患い、手術の後遺症で一時はほとんど声が出なくなったが、鬼気迫る闘病でこれを克服し、対がん協会の先生が10数年後に驚愕するほど長生きした。
私たち家族とは中学生の頃から同居を始めていて、浪人時代に私が受験勉強に打ち込んでいないのも知っていたが、何も言わなかった。最晩年までお洒落をしてススキノに出かけ、運転手を務めた私に「勉強ばかりしていないで、ヘルスでも行け」と小遣いをくれた。飲み仲間との合言葉は「転ぶな、飲みすぎるな、風邪ひくな」であった。私は、いちどは北大に入学したのに、休学、退学して医学部に再挑戦した後、それでも何度か失敗した。私が20代も親がかりでいられたのは、父が師事していた彫刻家 流 政之先生の「男は30までは何をしていてもいい」というありがたい?教えのためだったのだが、ついに27歳の時に札幌医大の不合格を祖父に伝えた時には、破顔一笑し、「もういいかげんいいことにしろや」と言い放った祖父であった。私は一緒に暮らしていてすこしずつの変化に気づかなかったが、肺がんが実は再発、進行していて、祖父はみずから限界を感じ取っていたのかもしれない。母には、私のことを「普通に就職して、結婚して、子どもを3人くらい作って幸せに暮らせばいい」と言っていたらしい(どういうわけか今では3児の父なのだから、祖父の言った通りになっている)。
不合格から数週後、母と北海道神宮にお参りに行き、帰宅して祖父の部屋におはぎを持っていった。何度か声をかけたが、返事は無く、ドアをあけると、祖父は床に両足を投げ出した格好でベッドにもたれて、息をしていなかった。その日の朝も母に換気のため窓をあけさせた後、「風邪をひいたら困るからそろそろ窓をしめてくれ」と頼んでいた祖父には、どこまでも生きることへの執念があった。思うにまかせぬ現実に悔しさをあらわにすることはあっても、闘病に関しての泣き言や愚痴は決して言わなかったから、最期まで病人と思えなかった。下を向いて黙ったままの祖父の表情は、まるで死ぬことはつまらないことだとでも言わんばかりに見えた。
数日後、祖父の遺骨と一緒に自宅に戻ってきたのとちょうど同時に、郵便配達員が家の玄関にやってきて、白い封筒を受け取った。開封してみると、果たして、それは旭川医大からの合格通知であった。その瞬間から全てが変わったと言っていい。だから、私は、私が医者になったのは、この祖父の所為だろうと思っている。そして、親戚達が私の旭川行きを思いのほか喜んでいて、それまでほとんど意識の埒外にあった旭川が祖父と母の故郷だったことを思い知った。それまで何年も何年も札幌の風は強く冷たかったが、それ以来、あらたな街と家族のルーツを再発見し、特殊な医学生生活の合間に一市民としての平凡な時間を楽しみ、休みのたび札幌との行き来を重ねていくうち、いつしか故郷は私にとって少しずつ優しい街に変わっていったのだった。
あれから20年がたち、1年半前にメンタルクリニックを譲りうけた私だが、病院勤めしか知らない身にとって、勝手がまったくわからず、夢中でここまでかけぬけた感じがする。最も古くから札幌の時を刻みつづける大通り一番街の風情に浮かれつつ、家族を養うためというのっぴきならない事情と、良きメンタルクリニックとして認められたいという願望をかかえて。
祖父は、数字でよくものを考える人で、「これから医者はあまるから、大変だ。ならない方がいいぞ。」と統計を見せながらその根拠を説かれたこともあった。どうやら、そういう時代はあと少しのところまで来ているらしい。しかし、私はまだ理想を持っている。それをどう実現したらいいか、考えているところです。